
INTERVIEW 08
“前例をくつがえせ!”
つくる / 建設部門
R.Yaegaki
神戸建設部
湾岸西伸第一建設事業所
2019年入社
理工学研究科 環境都市工学専攻 修了


入社を決めた理由
橋梁の設計の方針を決める初期段階から設計に携われること。インフラの整備や維持管理を通じて、社会や生まれ育った関西に貢献できること。

大切にしている信念
目の前のことを当たり前と思わず、常に問題意識をもって、本来どうあるべきかを考えることを大切にしています。
現在の仕事内容を教えてください。
世界最大級の連続斜張橋の設計に取り組んでいます
神戸建設部湾岸西伸第一建設事業所では、新規建設中路線である大阪湾岸道路西伸部における設計業務や工事監督を実施しています。その中でも、私は六甲アイランドとポートアイランド間に架ける「連続斜張橋」の設計業務を担当しており、主に設計コンサルタントの方々と協力しながら業務に取り組んでいます。具体的には、橋梁の設計に必要な基準の整理や耐震対策などの検討に加えて、新たな技術開発にも取り組んでおり、建設や維持管理にかかるコストや構造物の耐久性などの面において、より合理的な橋梁の実現を目指しています。この連続斜張橋は、世界最大級の長大橋となるため、その設計にあたっては、当社が過去に経験した阪神・淡路大震災の経験を踏まえて、既存の設計基準を活用しながら高度な設計手法を取り入れることが求められており、高い技術力が必要となります。設計コンサルタントの方々はこれまでの経験から貴重な知識や高い技術力を保有されているため、密にコミュニケーションを図ることで、それらをうまく吸収し、適切に連続斜張橋の設計へ反映することに努めています。
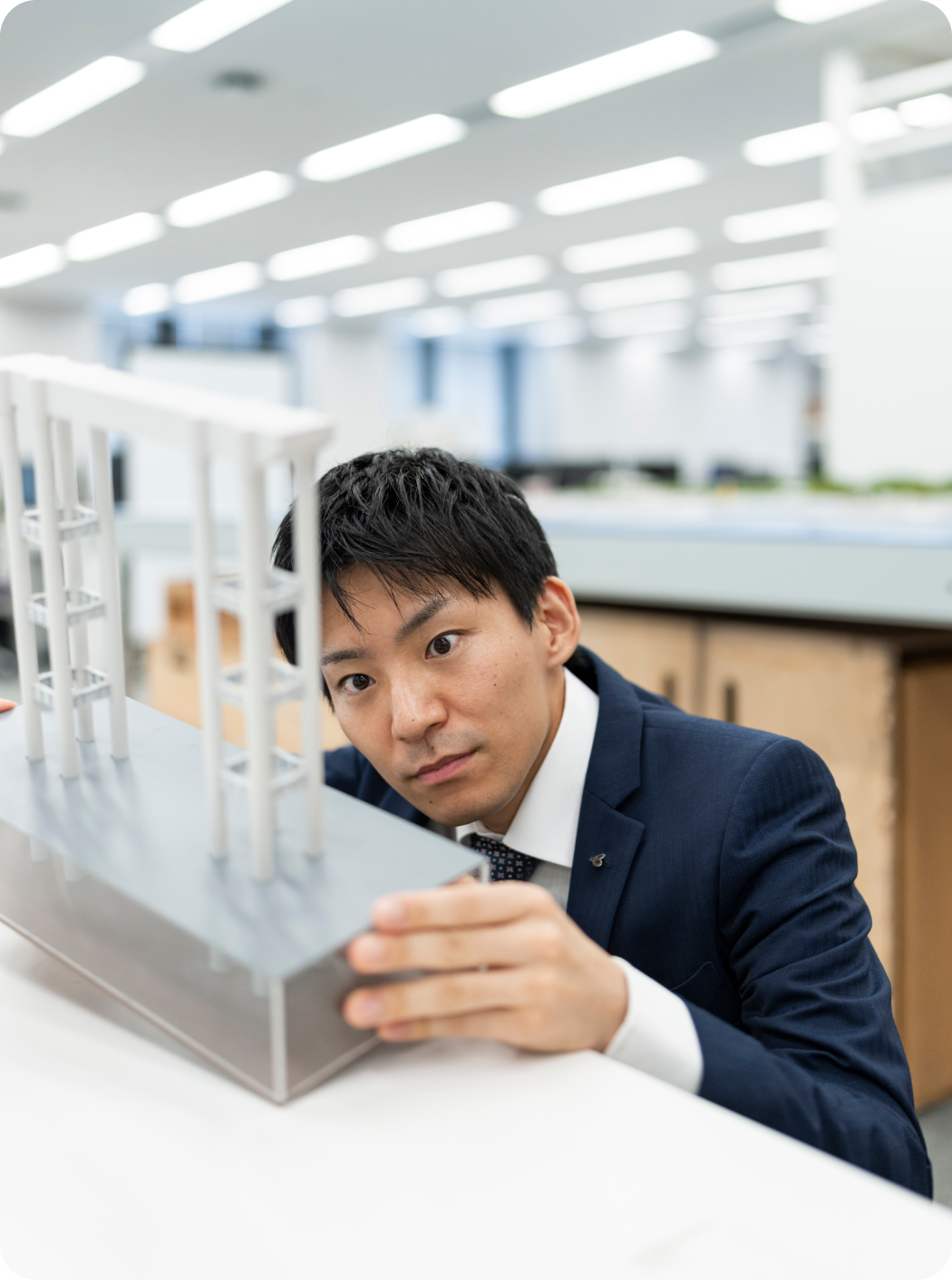
この仕事の魅力は何ですか?
前例に縛られず、解決策を自ら考えて実行できることです

目の前にある業務を深掘りすると、様々な課題が見えてきますが、それらを整理して、どのように解決するのかを自ら考えて実行できることが、当社の仕事の魅力です。例えば、営業中の路線で補修設計をする場合、都市高速道路ならではの厳しい制約条件があるため、理想的な設計をすることは難しく、制約条件を踏まえた最善策を模索します。その中で、設計の理論と現場の状況のバランスをよく考え、従来通りの慣例に縛られることなく、その時々の最適な1つの答えを見つけます。課題や困難なことも多く大変なこともありますが、最後にはそれが形となり、成果が目に見えて現れる瞬間は非常にやりがいを感じます。

これまでで印象に残っていることは?
困難な状況においても諦めずに工事を完遂したことです

大阪建設部に所属していた頃、私は大阪・関西万博開催時に新大阪駅や大阪駅などから会場へ向かうシャトルバス専用道路としての活用が予定されている淀川左岸線2期の豊崎IC(仮称)の整備の現場管理を担当していました。河川内に橋脚を施工し、桁を架設しなければならないことに加えて、一般国道と非常に近接した現場条件であることや厳しい工程を守ることも必要で、関係機関との協議が非常に困難な状況でしたが、決して諦めることなく、「どうすれば実現できるか」を社員一丸となって模索しました。年齢や役職に関わらずみんなで協力し、何とかして成し遂げようという熱意が途切れることはなく、最終的に目標を達成することができたことは非常に印象に残っています。

入社してから、一番成長したと感じることは?
バックグラウンドの違いを理解しながら調整する力がつきました
大阪建設部淀川左岸線2期事業調整室に所属していた際に、他の事業者に対して工事施工に伴い発生する技術的な課題や隣接工区との工事調整などに関する技術支援を行う業務を担当していましたが、その中で、当社にとっては当たり前のこととして議論していた内容が、関係先では通用せず、説明に苦労した経験がありました。当社では、課題への解決策について検討する際、予算・工程・品質といった要素を総合的に判断し、検討を進めていきますが、関係先ではそれらのバランスやウエイトを置く基準が異なっていることがあります。これは都市内で高速道路を建設・維持管理してきた当社のノウハウや企業風土も影響していると思いますが、課題解決のために、丁寧なコミュニケーションをとることで認識のズレや隔たりを解消し、お互いの考えを擦り合わせていきました。このような経験から、相手の意見や考えを尊重した上で、目の前にある業務が、なぜ今そうなっているのか、今後はどうあるべきかを常に考えることができるように成長できたと思います。
職場の雰囲気はいかがですか?
声を上げたら絶対無視されない、誰かが声を拾ってくれる会社だと思います
現在の職場では、一人ひとりが役割に応じて様々なことを判断しながらも、事業全体に関わる相談事や情報共有は密に実施されており、フォローアップも頻繁に行われています。プライベートでの交流もあり、社員同士が気軽に本音で話し合える関係が築かれていると思います。声を上げれば、必ず誰かが拾ってくれる風土があり、絶対に無視されることがない点も大きな特徴です。また、当社はジョブローテーションという働き方が特徴的で、担当者間で業務を引継ぐことが多いですが、これまでの考えを踏まえつつ、新しい視点を取り入れていくなど、常に柔軟な発想を持って業務に取り組む姿勢が求められる職場だと感じています。


大切にしている「当たり前」な習慣やルールはありますか?
組織ごとの文化や価値観、考え方を
尊重しながら丁寧に調整することです
例えば、設計業務の検討において、社内では留意点や優先事項などについて、ある程度の共通認識を持ちながら検討を進めることができます。一方で、対外的に協議をする際は、前提の認識が異なることや方針の一致に時間を要することがあるほか、場合によっては「なぜその方法を選ぶのか」という根本的な部分から議論が始まることもあります。また、高速道路を建設する段階から将来の維持管理性を考慮することなど、今のうちに検討・対応しておく必要があるような当社の要望をうまく伝えながら、相手の意見や要望についてもしっかりと聞くことが求められます。そのため、対外的な業務を進める上では、組織ごとの文化や価値観、考え方などを尊重しながら丁寧に調整することを心がけています。当社にとっては当たり前のことでも、その理由や背景などを自分の言葉で丁寧に説明し、お互いが納得した上で業務を進められることが重要だと思います。

阪神高速でこれからどのような「当たり前」を描いていきたいですか?
前例や自らの考えを当たり前とせず、失敗を恐れずに挑戦し続ける
自分や当社にとっては当たり前と思っていた考えが、周囲には通じないこともあります。そのような時は、論理的かつ丁寧に説明する力が重要だと経験を重ねる中で学んできましたが、これからも自分の考えを当たり前とせず、異なる立場や意見を尊重しながら、柔軟に課題に向かっていきたいと思います。大規模なプロジェクトでは、多くの調整や意見交換が求められますが、全員が納得できる形を追求しながら最適な結果を目指す姿勢を大切にしたいです。また、前例や過去の技術を参考にしながらも、新たな技術も積極的に取り入れるなど、どんな時も失敗を恐れず、挑戦し続けることで、さらなる成長を目指していきたいです。




入社後の経歴
※部署名は当時のものです。
まもる
まもる
管理企画部 保全技術課(2019)
つくる
つくる
大阪建設部 淀川左岸線建設事務所(2021)
つくる
つくる
大阪建設部 淀川左岸線建設事務所(兼)大阪建設部 淀川左岸線2期事業調整室(2022)
つくる
つくる
現在
神戸建設部 湾岸西伸第一建設事業所(2023)
ある日の1日
スライドワーク
9:30
9:30
出社(スケジュールの確認とメール確認)
10:30
10:30
設計コンサルタントと橋梁の設計業務に関する打合せ
12:00
12:00
昼食
13:00
13:00
設計業務に関する社内打合せ
13:30
13:30
新規技術開発に関する共同研究の相手先と打合せ
14:30
14:30
設計業務課題の検討、整理(事務作業)
16:00
16:00
業務課題を所長へ説明
17:00
17:00
メール返信対応
18:00
18:00
退社
その他インタビュー
ENTRY
担当者一同、
皆様のエントリーをお待ちしています
ENTRY

