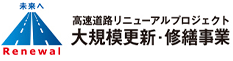1974年に開通した16号大阪港線の阿波座付近は、13号東大阪線と1号環状線から神戸方面や天保山方面へ向かう交通の分合流部です。1997年、渋滞解消のため3車線から4車線へと車線拡幅工事が行われましたが、その際、路下の制約により、既設桁と同じ位置で拡幅した新設桁を支持できず、新設桁のみを支える橋脚を新たに設置。さらに新旧の桁の境目にゴム製の伸縮装置(縦目地)を設置して走行面を連続化しました。しかし、この縦目地の損傷により通過騒音などの不具合が発生。長年、さまざまな対策を講じてきましたが、抜本的な解決には至っていませんでした。
そこで、騒音低減、走行性向上を目指し、縦目地の解消と主桁の取り替えという大規模工事が行われました。2022年6月から2カ年弱をかけた工事の概要、ポイントなどについて、担当者にインタビューしました。
 管理本部 大阪保全部 改築・更新事業課
管理本部 大阪保全部 改築・更新事業課杉村 泰一郎(課長代理)
 管理本部 大阪保全部 改築・更新事業課
管理本部 大阪保全部 改築・更新事業課木村 太郎(担当)
路面に設置された縦目地が不具合の要因だったとのことですが、
縦目地とは珍しいものなのでしょうか。
杉村 縦目地構造そのものは高架道路の分合流部などで一般的に見られる構造ですが、ここは約600mという長い区間に渡って第一走行車線の中央に設置してある、かなり珍しい形式です。

1997年の工事では、3車線を支える既設のT字型RC橋脚の間に、拡幅した桁のみを支える逆L字型鋼製橋脚を設け、既設桁と拡幅桁は異なる橋脚で支える構造としました。そのため、既設桁と拡幅桁は連結せず、橋面上で縦目地を設置し両桁の路面を接続させています。既設桁と拡幅桁の支点位置が異なる、つまり、それぞれ別々で支えているので、両者の間にたわみ差が生じてしまったのです。縦目地は第一走行車線のど真ん中を通っているため、車両が動きの違う新旧両方の桁をまたぎながら連続的に進むので、それによる擦れや損傷につながり、異音などの不具合が生じたのです。
工事前の既設橋脚部 断面


その縦目地解消のため、どのような工事を行いましたか。
杉村
既設桁と拡幅桁のずれている支点の位置を既設橋脚に合わせる、つまり支点位置を統一しました。既設のRC橋脚の拡幅桁側の梁を伸ばして拡幅桁も支えるようにし、両桁の動きがまったく同じになるよう97年に建造した桁を取り壊し、新しい桁に架け替える方法をとりました。
これによってたわみ差をなくし、縦目地構造を解消することとなりました。この工事の最大の特徴は都市中心部という狭く制約が多い現場における主桁の取り替えです。これだけの大きさのインフラ構造物を壊して取り替えることは、かなり珍しい工事だと思います。
工事後の既設橋脚部 断面


木村 耐震性向上も重要です。新しく架け替える桁の重さが元々の橋脚に乗ってくるわけですから、そのままでは最大級の地震動に対して耐震性が不足してしまいます。下の一般道は中央大通りの本線と側道で交通量は非常に多く、制約があるため、既設のRC橋脚を太くするなどの対策はできませんでした。そこで、橋脚の補強として外側からPCケーブルで締め付けたり、その上に乗せる新しい桁を鋼製の軽い桁として重さをできる限り軽減させました。また、最大級の地震動で生じる水平力、いわゆる横揺れへの対応として、元々の拡幅桁を支えていた鋼製橋脚も反対側に拡幅して水平力に対応する装置を設置、補うことによって、橋梁全体で耐震性を確保しました。

工事を進める中で苦労された点、工夫された点をお聞かせください。
杉村
これほど大がかりなものを壊し、新たに持ってきて架ける大規模修繕工事で、元々あった橋脚をいかに有効活用するか、既存のものを上手に使える状態にするかが今回の設計で一番難しいところでした。また、工事音についても壊す方が造るよりも大きな音がしますし。試行錯誤しながらもしっかり対策を取って進めてきました。
たとえば、元々のRC橋脚に新たにコンクリートを継ぎ足して拡幅部分を造る際、流れやすい高流動コンクリートを使い、流し込む型枠も透明のものを採用して、隅々までしっかりコンクリートが入っていることを目視で確認できるようにしました。さらに打設状況のモニタリングなども行いました。安全性を念には念を入れて確認するためです。元々あるものの形に合わせながら造るために、施工方法も一つ一つ検討を重ねました。
加えて、非常に狭く限られた工事現場だったことも苦労した点です。下の一般道は交通量も人通りも多く、高速上も3車線が通っている。その環境の中で、交通影響や騒音に十分配慮しながら、確実に工事を進めなければならず、さまざま工夫を施す必要がありました。
たとえば、コンクリート構造物を壊すときには、通常、騒音や粉じんが発生するので、音が少ないカッターで細かく切断した上で搬出したり、分厚い防音マットや粉じんシートで隙間なく囲うなどできる限り対策を講じました。
木村 作業時間も非常に限られており、交通影響が少ない夜間に規制を広げて工事を進めるよう、総合的に考えながら工法を選定しました。
交通影響や音など、警察との協議や地元状況も現地確認しながら、工事に入る前から入念に検討した上で、現場作業が始まってからもその都度、必要な対策を行ってきました。





多軸台車での運搬(夜間)
工事状況に応じて、工法などを変更することも多かったのですか。
杉村
設計図通りにいかないことは多々ありました。現地を確認したところ、97年当時の図面とは数ミリ単位でのズレが出ていたり、サビなど経年の損傷が進んでいる箇所が発見されたり、その都度工事に入る前には十分に確認して工事を進めていきましたが、時には一旦工事を止め、対策を検討した上で次の工程へと進めることもありました。
また、特に工事音関係で工法を変更することは多かったですね。都心部ですから、低騒音の工具を使うなど基本的な対策はしていたのですが、いざ工事を進めると音が反響する等により近隣住民の方々にご迷惑をおかけしてしまうこともありました。その都度、対策を加えて現地を確認しながら工事を進めていきました。
今回の工事はこのような、いわゆる現地合わせで対応せざるを得ないことが多く、頭を悩ませましたが、しっかりとした構造物を造るため、妥協することなく検討を重ねました。その都度、工事関係者と集まって相談し、工法を考え、対策を行うようにしました。近隣住民の方々にも「こういう対策をします」「音が鳴る作業を何日何時にします」とビラや掲示板により作業内容をお知らせするなど、具体的に丁寧に情報提供しながら進めていきました。私自身は特に壊す作業が、毎日神経をすり減らす大変な作業でした。
非常に困難な工事でしたが、
予定より約4カ月前倒しで無事に工事完了となりました。
木村 おかげさまで、縦目地構造の解消という当初の工事目的を達成できたことで、騒音が低減され、走行性が向上しました。工事を安全に予定通り着々と進めた上で、少しずつ工程を短縮することによって予定よりも約4カ月早く高速上の固定規制を解除でき、工事によって発生していた渋滞の影響を極力減らせたかと思います。
杉村 都市部の狭い作業スペースでは、抜本的に工程を早める工法などはありません。また周囲の安全や騒音などの様々なことに気を付けながら工事を進める必要があります。1つ1つの作業を着実に行い、大きな遅れを生じさせずに、できる限りの効率化を図った積み重ねが工程短縮につながったと思います。


工事を終えての感想をお聞かせください。
木村 都市部における非常に制約の多い難工事でしたが、計画、設計の段階から多くの社員らが携わり、事業を完遂することができて心からよかったと思っています。高速上の固定規制の早期解除に向け、大阪保全部だけでなく、工事受注者、関係者が一丸となって、ともに取り組んだ一体感が今も忘れられません。入社間もないうちからこのような大規模事業に携わることができ、やりがいを感じるとともに、非常に勉強になりました。本体工事終了後も、路下の街路復旧工事まで無事に完了することができ、嬉しく思っています。
杉村 今まで携わってきた新たにものを造ることとは異なる点が多く、設計図通りにいかないことも多々ありました。その都度、現地をよく確認して、安全性はもちろん、維持管理性にも十分考慮し、施工内容を判断することが必要でした。時には現場を止めて設計しなおすことも必要になりましたが、今後、何十年もの間、安心して利用できる道路を造ることを考え、決して妥協せずに議論を重ねて工事に取り組みました。土木技術者として大変貴重な経験でした。この経験を活かして、引き続き、安心、安全、快適に阪神高速をご利用いただけるようにリニューアル工事を進めてまいります。
(※本文に記載の内容はインタビュー当時のものです。)