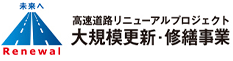大阪都心部と松原市など大阪南東部や奈良方面をつなぐ14号松原線。その喜連瓜破付近の橋梁架け替え工事が約2年半のときを経て完成し、2024年12月7日に通行を再開しました。密集市街地内を通る高速道路の一部分(喜連瓜破⇔三宅JCT間)で長期にわたる完全通行止めを行い、周辺環境や交通への影響を極力抑えるため、世界初の工法による「前代未聞」と言われる工事となりました。
2022年6月1日から始まった工事の背景。工事内容、交通影響対策などについて、担当者のインタビューから振り返ります。
計画と準備
 大阪保全部 改築・更新事業課 課長(当時)
大阪保全部 改築・更新事業課 課長(当時)田畑 明子
(設計・現場監督を担当)
工事着手前はどのような状況でしたか?
田畑 1980年に開通したのですが、比較的早い段階から橋桁の中央部が沈下し始め、想定を上回る “垂れ下がり”が進行し、路面が大きく沈下していました。その対策として、橋桁の下部に設置したケーブルを両側から引っ張り補強していたのですが、抜本的な解決には至っていませんでした。
そこで長期の健全性・耐久性を確保するために、既存の橋桁を撤去し、橋脚を一部活用しつつ、1本の連続した鋼製橋への架け替え工事を実施することとなりました。
工事のために約3年間、高速道路の一部分(喜連瓜破⇔三宅JCT間)を終日通行止めにするという国内で初めての大きな決断をしました。どのように検討されたのでしょうか?
田畑 橋がまたぐ「瓜破交差点」は、対向7車線の長居公園通を渡っており、通行を止めるわけにはいきません。そこで、工事箇所に仮設のう回路を設置する案など複数案を検討しましたが、工期が10年以上かかるものばかりでした。最終的に3年間(当初想定)の終日通行止めを行い、集中的に工事を実施することが、一般道への交通影響が少ないなど、地域の皆さまをはじめ社会への影響を最小化できる最善の策と判断しました。
そして限られた工期、周辺への影響を最小限に抑えるために、世界初となる工法が取り入れられたのですね。どのような施工方法でしょうか?
田畑 地上からの既設橋桁撤去はほぼ不可能なので、空中での撤去作業を行う工法を編み出しました。 大きく3つのステップで、まず、元の橋桁の上に仮設の橋「仮設桁」を設置し、次に、その仮設桁をレールとして用い、元の橋桁をバラして吊り上げて撤去していきます。その後、仮設桁を撤去し、3分割してあらかじめ組み立てた新しい橋脚と桁(南北の側径間と中央径間)を、夜間のうちに移動し新橋梁の架設を行うものです。
検討する中で特に苦労したことは?
田畑 通行止めが了承されるまでが最も大変でした。2025年4月から始まる大阪・関西万博までの工事完了を目指し、スケジュールを厳密に管理していきました。施工会社と知恵を絞り日単位の工程短縮案を検討、何度も練り直して詳細設計を行い、警察ほか数多くの管理者との協議や地域の方々への説明、学識経験者を含めての検討会など、さまざまな課題を関係者らが一丸となり粘り強く進めていきました。
私自身は部下や同僚とお互いを尊重し、協力し合える雰囲気づくりに努めました。目標どおり2022年6月1日から通行止めを開始、工事が着工できたことは、私にとって生涯忘れられない経験となりました。


交通影響対策
 大阪保全部 保全管理課 課長代理(当時)
大阪保全部 保全管理課 課長代理(当時)牧野 統師
(広報や交通影響検討を担当)
長期間の通行止めにあたって、周辺の交通渋滞発生が予想されましたが、どのような交通影響対策を検討、実施しましたか?
牧野 通行止めの半年以上前から具体的な検討を進め、どのような形で交通影響が発生するのか、しっかりとシミュレーションした上で対策を計画しました。その上で、通行止めの広報においても、通常は3か月前から実施するのですが、今回は半年前から実施しました。う回ルートの情報を図形情報板などで提示したり、一般道路でも、う回乗継ルートの案内看板を立てるなど、行いました。
また、特設サイトを設け、交通予測などの必要な情報を、その都度提供していきました。テレビやラジオでのCMのほか、交通広告、インターネット広告など、幅広い方法を用い、より多くの方に伝わるようにしました。
さらに、期間中に交通状況が変化することも想定し、常に交通状況を観察しながら、状況に応じて柔軟に対策を講じてきました。
継続的にリアルな交通状況をお伝えし、対策も取られたのですね。
牧野 本工事のように長期間で広く交通影響が及ぶ場合には、従来の情報提供だけでなく、工事の進捗をお知らせする交通広告の掲出や、速報的にSNSで工事の進捗写真を掲載するなど、より直感的に伝わる手段を用いて工事の進捗をお伝えするようにしました。
工事中のお問い合わせに対応するために、専用のコールセンターを設置しましたが、そこに寄せられるご意見とともに、随時実施してきたモニタリングを軸に、影響が大きい箇所への対策を打っていきました。
「前代未聞」の工事なので、先入観は一切持たずに検討しようと対応にあたりました。ご利用のお客さま、地元の方のご協力あってこそ、工事がスムーズに進捗するとの考えから、常に「情報共有」を行うことが非常に大切だと考えています。

通行止めと工事開始 仮設桁の設置(STEP.1)
 大阪保全部 改築・更新事業課(当時)
大阪保全部 改築・更新事業課(当時)中田 諒
(STEP.1 現場監督を担当)
2022年6月1日、いよいよ終日通行止めとなり、まず仮設桁設置に取りかかりました。どのような工程でしょうか?
中田 仮設桁は、解体撤去が空中で完結する、世界初の工法を実現するための主軸、「命の部材」です。撤去する橋の上に仮設桁を設置し、そこに移動式の作業足場や運搬台車を取り付け、 既設橋梁のコンクリートの切り出し、切り出したブロックの搬出をすべて上空で行いました。既設橋梁の中央部から外側に向かって15個の部材を組み立て、全長165mの仮設桁を構築しました。
そのポイントは?
中田 仮設桁は重さ1200トンで、これほどの規模の構造物とこれらを組み立てる大型の施工機械が高架橋上に設置される事例は極めて少ないのです。荷重による構造への悪影響がないか事前に解析で確認し、施工機械は橋の耐力が期待できる位置に配置するなど、慎重に進めていきました。さらに、元の橋梁の中央ヒンジ部が垂れ下がっている状態だったことを踏まえ、橋が施工中に想定外の動きをしていないか、計測管理体制を充実させながら進めました。
仮設桁の耐震性についても、役割が終わればすぐに撤去されるとは言え、車や歩行者が行き交う一般道の直上で工事を行うことから、最も高いレベルを設定して進めました。
特に工夫したことは?
中田 仮設の構造物とはいえミリ単位で精度よく組み上がっているか、日々確認しながらの工事でした。高速道路の幅員は19mと、組み立てる構造物や施工機械にとってはかなり狭く、路下では車や歩行者が行き交っていることから、特に落下物対策には力を入れました。クレーンが高速上から必要以上にはみ出さないようレーザーバリアを設置したり、落下防止ワイヤー付きの工具を使用するなど工夫しました。
どんなところに苦労しましたか?
中田 高速道路本線を止めての工事なので、工期の厳守は絶対です。仮設桁構築の時点からこまめな進捗管理が求められました。日々、どれほど仮設桁が組み上がったか確認しつつ、次に控える工種のための調整・協議も並行して進めていました。また、夜間に行う交通規制の影響をいかに小さくできるか、規制の形状や広報の計画、警察との協議などさまざまに検討を重ねました。
架設桁の設置は本工事の最初の大きな作業だったので、非常に緊張感がありました。事前に解析した上で臨んでいるとは言え、垂れ下がっている中央ヒンジ部に最初の部材を設置後すぐにお盆の休工期間に入ってしまい、心配で帰省中もライブカメラを度々確認していました。
苦労は多々ありましたが、担当者全員で課題や困りごとを共有し、分担して乗り越えていきました。仮設桁が完成したときには大きな達成感を得られました。


既設橋梁の撤去(STEP.2)
 大阪保全部 改築・更新事業課 主任
大阪保全部 改築・更新事業課 主任森 謙吾
(STEP.2 現場監督を担当)
2023年1月11日から6月まで約5カ月をかけて、既設橋桁の撤去を行いました。どのような工程でしたか?
森 まず、仮設桁に設置された4基の移動台車内で、コンクリートを低騒音工法であるワイヤーソーを用いてブロック状に切断しました。切断したブロックは1つ4~8トン程度で、作業用クレーンで運搬台車へ。そのまま端まで運び、クレーン車で大型トラックへ積み、搬出しました。搬出したブロックは合計約1300個にのぼりました。
端から順番に削っていったのですが、中間橋脚を中心として、やじろべえのような形になっており、バランスよく撤去していくため計画段階で解析によりシミュレーションを行い、バランスがどの程度ずれても大丈夫か、定めていました。安全管理のため、実際に一断面切るたびに桁がどれほど下がるか計測しながら、解析どおりに撤去を進めるよう徹底しました。
移動作業車が最初に移動した際にできた、かつて高速道路があった空間部分を見て、担当者ながら、空中で撤去が進むことが本当に実現されたのだと改めて驚きました。同時に安全に進めていくぞと身が引き締まる思いでした。
この橋梁には補強ケーブルという他の橋梁にはない特徴がありましたが、どのように撤去したのでしょうか?
森 切断作業を進めながら、2月に補強ケーブルの引き抜き作業を行いました。ケーブル自体も非常に重く、1本80mで2トンほどあったので、引き抜く作業は非常に困難だったのですが、何とか1夜間、ぎりぎりの時間帯で完了することができました。
作業は昼夜連続で行いましたが、特に工夫したことは?
森 路下交差点の交通影響を最小限にとどめるため、工事でどうしても必要な規制は夜間のみとし、作業時間は午前9時~翌2時で、2班体制で施工を進めました。仮設桁などの撤去設備や、低騒音のワイヤーソー工法、移動作業車の内部に吸音マットを採用するなどし、地元のご理解を得ることができました。事前にワイヤーソーによる撤去騒音の低減を体験していただくイベントを開催したことも、環境対策への一定の理解につながったのではないかと思います。こうして昼夜連続で撤去作業を行えました。
路下の一般道路を通行止めせずに施工するため、撤去している移動作業車からはコンクリート片はもちろんのこと、雨水も決して落とせません。移動作業車の底面に防水シートを施工し、底面に溜まった雨水を排水するポンプを設置したり、大雨の後には排水状況や防水シートの確認をこまめに実施。また、切断したコンクリートブロックの重量を管理し、ブロックに重量を明示することで、搬出時の過積載の防止につなげるなど、徹底して安全に配慮しました。
橋桁の撤去後、8月からは仮設桁の引き戻しを行い、10月に完了。11月から翌年2月にかけて、橋脚の頭部の撤去を行いました。約6600トンにもおよぶコンクリートが姿を消し、2024年3月、既設橋梁の撤去が完了したのです。



工事を支える取り組み
 大阪保全部 保全管理課
大阪保全部 保全管理課森岡 寛太
(広報や交通影響検討を担当)
工事の必要性を広く知っていただくため、どのような広報活動をしましたか?
森岡 地元の方々やご利用いただくお客さまのご理解、ご協力があってこその工事ですから、皆さんに寄り添ったご案内ができるよう、担当者一同が一丸となって対応しました。特に本工事は長期間にわたるので、より広い範囲の方々へのきめ細やかな情報提供が必要と考え、今まで以上に多くの種類の広報を手厚く行いました。
今までにない、新たな取り組みはありましたか?
森岡 工事の概要や進捗状況をより多くの方々にお伝えしようと、瓜破交差点南東角に、誰でも気軽に立ち寄れる「情報館」を開設しました。工事概要の動画をはじめ、工事現場の中に入ったような雰囲気を体験していただけるVRや、現在、どのような工事が進んでいるのかライブ配信するなど行っていました。大変多くの方々にご来場いただき、ご質問もたくさん頂戴しました。注目度の高さを実感しました。応援メッセージをいただいたこともあり、とてもうれしかったです。
また、地域の方々に向けてイベントも複数回実施し、小さなお子さんにも工事内容が伝わるよう、工夫を凝らしました。さらに、地元の小学校に向けた出前授業も実施しました。スライドなどを使った説明や、クイズコーナーなどを用意し、楽しく理解してもらえるよう説明しました。地域の方々に、わが町で世界初の工事が行われていると誇りに思っていただけるように、またお子さんが将来、土木業界に興味を持っていただければと、広報活動を進めていきました。
技術者を対象とした「現場見学会」も行いました。
森岡 技術者をはじめ、他の道路事業者、大学の先生、有識者、鉄道の橋梁関係の方々など、計130回ほど開催し、約1300人に見学していただきました。
インフラの老朽化が叫ばれる中、これまで架け替えというアプローチが難しかった橋に対しても、架け替えの選択肢があるのだと知っていただき、業界全体で今後のインフラの維持管理に役立てていただけたら幸いです。
社内向けの見学会も行いました。事業のスケール、意義をあらためて認識し、モチベーションアップへとつなげていくことが一つの目的でした。私たち阪神高速は企業理念として「先進の道路サービスへ」と掲げていますが、修繕する、造り直すだけではなく、新しい価値を技術によって創り出す、その継承も大切だと考えています。




新橋梁の架設(STEP.3)
 大阪保全部 改築・更新事業課 課長代理
大阪保全部 改築・更新事業課 課長代理渡辺 真介
(STEP.3 現場監督を担当)
2024年4月、いよいよ「新設橋梁の架設」が始まりました。どのような工程でしたか?
渡辺 まず、左右両側にある橋脚の頭部を再構築し、その後、本線の高速道路上の施工ヤードであらかじめ組み立てておいた鋼製橋桁を、巨大な多軸台車を使って、まず左右両側から送り出して架設。最後に、近郊のヤードで組み立てた中央の橋桁を、一括で吊り上げて架設完了しました。あとは舗装などの仕上げとなります。
工事のポイントは?
渡辺 架設工事の山場となる合計4回の架設作業では、交差点の初めての大規模な通行止めを伴うため、通行止めを行った上でいかに影響を小さくするか、という点が最も大きなポイントでした。
当初、新設する南北2本の橋脚を多軸台車により複数日に分けて架設する予定でしたが、2台の大型クレーンを交差点中央に配置し、南北同時に1夜間での一括架設を行うことができました。その理由は、新設橋脚の構築範囲の精査により軽量化が実現したことや、橋脚の切断位置を変えるなど、現場で工夫をしながら、なるべく元々あった柱を活かしながら新しい橋脚の頭部を架設する計画に変えたこと、また、本線上の空間を利用して新しい桁を構築していたので移動させるのが最短距離で行えたことなどが挙げられます。こうした工事内容の精査、手法の見直しの積み重ねが大切で、高い安全性を保ったまま工期の大幅な前倒しが可能となりました。
路下交差点の初めての全面通行止めについて、どのように進めましたか?
渡辺 6月1日、15日に、南北の両側の橋桁の架設を同じ手順で、それぞれ1夜間で実施しました。高速道路上で組み立てた約500トンの側径間部の橋桁を、送り出し装置と合計4基の多軸台車を駆使して、前方に約58m送り出す作業でした。今までに幾度も行っていた交差点の夜間規制は、22時から開始していましたが、今回の作業は工程上22時からでは午前7時までに完了させることができないため、少し前倒し、20時から開始しました。慣れない作業も多く、初回の工事では想定以上に時間がかかりましたが、何とか所定の時間内に作業を完了させることができました。この初回の経験を活かし、2回目は余裕を持って作業を進めることができました。
中央部の架設は9月14日に行いました。先に架設した両方の側径間部の橋桁に取り付けた吊上げ装置によって中央部の橋桁を吊上げました。これによって新しい橋桁がかたちを成し、時間内に交差点の通行止めを開放できたことで一安心しました。
特に気をつけていた点、工夫した点は?
渡辺 通行止めによって、周辺の交差点での渋滞、混雑により大きな影響が出ないか、歩行者や自転車の必要な導線を確保しながら工事が実施できるか、さらに、1夜間の通行止めのうちに必要な架設作業を完了させることができるか、十分な検討が必要でした。 架設作業時間については、施工者と工程の見直しや細かな調整を繰り返し、4回の架設作業はいずれも1夜間のうちに工事を完了させることができました。ただ、6月1日の橋桁の架設作業では、交差点周辺で想定以上の交通集中により、多くの方にご迷惑をかける事態を招くこととなりました。もう少し慎重に検討すべきだったと猛省しています。以降は反省を踏まえ、交通影響もなんとか想定内に抑えることができました。
新しい技術は導入されましたか?
渡辺 さまざまな新技術を取り入れています。例えば、アスファルトが乗る面には「サラボルト」を採用しました。皿型のボルトで、ボルトの頭が出ていないので、打ち替えのときに塗装がめくりやすかったり、十分な厚さが確保できるため、維持管理性の向上につながります。他にも鋼製床版など耐久性にすぐれたものを取り入れており、100年先も安心して利用できる高速道路を目指しています。
専門家だけでなく、地域の方をはじめ一般の方々の関心も高かったようですね?
渡辺 それぞれ約500トンある巨大な南北の橋桁を、高速道路の面上から送り出し、多軸台車を用いて運び込んだのですが、夜遅くの工事にも関わらず、多くの方が交差点の周りで見届けてくださいました。最後の中央部の桁の架設工事では、多軸台車で交差点の中央まで運び、そこから吊り上げていく様子を、約1,500人の方が熱心に見守っていただき、工事への関心の高さをひしひしと感じました。
工事着手前は、社内で誰もが「こんなところでこんな工事ができるのか」という思いが強かったかと思います。地元の方やご利用されるお客さま、関係管理者など、多くの方々のご協力、同意を得ることは大前提ですが、既存技術の組み合わせや創意工夫によって、いかなる大規模な更新事業に対しても工事実施できる可能性を強く実感できました。
架設をすべて順調に終え、その後は供用再開、通行再開に向け、一日でも早い通行再開を行うことが私の使命だと思いつつ、残りの工事を行っていきました。




開 通
地域の方々、ご利用のお客さまにご理解とご協力をいただき、2024年12月7日 午前4時40分、14号松原線(喜連瓜破~三宅JCT)の通行を再開することができました。2022年6月1日から2年6カ月、当初の予定より約4カ月早い通行再開となりました。皆さまに心より感謝申し上げます。 阪神高速は、100年先も、安全・安心・快適にご利用いただけるよう、先進技術と創意工夫を持って「高速道路リニューアルプロジェクト」を推進してまいります。

【喜連瓜破 橋梁架け替え工事】
二年半の軌跡 ~100年先を見据えて~(ロング版)