2010年12月18日、神戸市を南北に結ぶ阪神高速神戸山手線の神戸長田出入口-湊川ジャンクション間(約1.8km)が開通し、海側の神戸線と山側の北神戸線がつながった。
2つの高速道路を接続する湊川ジャンクションを建設するにあたり、阪神高速では次世代型とも言えるユニークな基本方針を掲げた。それは、すでにそこにある構造物を積極的に流用し、建設・解体工事だけでなく修復工事も同時に行ってしまおうというものだ。
その背景にはコスト削減と、通行止め期間をできる限り短縮するという大命題があった。
しかし、改築、撤去、修復、設計施工などを同時進行しなくてはならない現場は、作業が複雑多岐にわたる上に施工に携わる技術者も多く、いつも以上に緊密なコミュニケーションが必要となる。しかも現場のすぐ近くを新湊川が流れており、工事の約半分が河川上での作業となるため、渇水期に施工しなくてはならないという地理的条件も重なっていた。
どのようにしてこの複雑な工事をやり遂げたのか、建設事業本部建設技術課の主任として設計を担当した大嶋昇と、現場監督をつとめた杉村泰一郎に話を聞いた。


その際に新設する連結路を、湊川出入口の出口と入口の間に割り込ませる形で取り付けることになっていました。
すべてを撤去してから新しく造り直せば話は早いのですが、その場合は長期間の通行止めが必要となり、お客様に多大なご迷惑をかけることになってしまいます。
またできるだけ無駄な出費を抑えたいということや、撤去によって大量の廃棄物が出るのを避けたいということもあり、既存の構造物の使える部分は活用し、必要な部分だけを取り替えることになりました。
図を使ってご説明しましょう。
これは西行出入口のある南側のものです。


仮に西行入口を1としますと、この1は取り壊して西側にずらした形で新たに造り直しました。そうしておいて、2の西行出口との間にできた隙間に山手線への連結路である3を割り込ませたということです。
ところで2と3ですが、川の上を通るカーブのところで分岐していますよね。(4)
これが先程から話題になっている、既存の構造物を流用するように工夫した1つの例です。

 GISを活用した情報共有プラットフォーム「COSMOS-GIS」
GISを活用した情報共有プラットフォーム「COSMOS-GIS」 高架道路上パーキングエリアの設計・施工
高架道路上パーキングエリアの設計・施工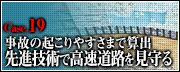 新交通管制システム
新交通管制システム 工事情報等共有システム「Hi-TeLus」
工事情報等共有システム「Hi-TeLus」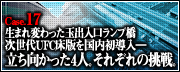 15号堺線玉出入口ランプ橋 リニューアル工事
15号堺線玉出入口ランプ橋 リニューアル工事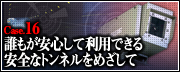 炎強調システム&WDRカメラ
炎強調システム&WDRカメラ 橋梁模型製作コンテスト
橋梁模型製作コンテスト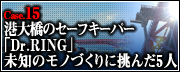 Dr.RINGプロジェクト
Dr.RINGプロジェクト スーパーコンピュータ「京」を使った技術的挑戦
スーパーコンピュータ「京」を使った技術的挑戦 都市部道路トンネルの換気所設計
都市部道路トンネルの換気所設計 阪神高速独自のフレッシュアップ工事
阪神高速独自のフレッシュアップ工事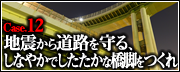 日本初、鋼管集成橋脚の開発と実用化
日本初、鋼管集成橋脚の開発と実用化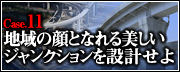 三宝ジャンクションの景観設計
三宝ジャンクションの景観設計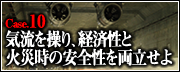 日本初、インバータ制御ジェットファンによるトンネル換気と排煙制御
日本初、インバータ制御ジェットファンによるトンネル換気と排煙制御 阪高 SAFETYナビを活用した交通安全施策
阪高 SAFETYナビを活用した交通安全施策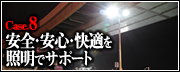 日本初、高速道路本線用LED道路照明
日本初、高速道路本線用LED道路照明 交通管制システム
交通管制システム 保全情報管理システム
保全情報管理システム 地震対策(免震構造・制震構造)
地震対策(免震構造・制震構造) 下弦ケーブルを用いた有ヒンジラーメン橋の補強設計と施工
下弦ケーブルを用いた有ヒンジラーメン橋の補強設計と施工 アルカリ骨材反応対策
アルカリ骨材反応対策 鉄道函体アンダーピニング下に構築する開削トンネルの施工技術
鉄道函体アンダーピニング下に構築する開削トンネルの施工技術 湊川ジャンクション改築工事
湊川ジャンクション改築工事