2008年7月、港大橋の地震対策は完了した。設計を始めてから6年を費やしたプロジェクトでは、「床組免震」「制震ブレース」以外にも、構造再生のための補強が細部にわたって施され、大阪港のシンボルである赤い橋は見事に再生を果たしたのである。
続いて2009年には東神戸大橋、2010年には天保山大橋の2つの長大橋においても、免震・制震をコンセプトに地震対策が図られた。東神戸大橋については、「縦置きサンドイッチ型積層ゴムダンパー+ケーブル」が取り付けられ、天保山大橋においては、塔下部の斜材と水平梁が交わる接合部(ガセット部)に「せん断パネルダンパー」が設置された。
東神戸大橋は、もともとゆっくりゆれる免震構造の橋でした。
港大橋のところでご説明したように、普通の橋は何らかの形で主塔部と主桁を固定していますが、この橋は固定していません。ブランコのように揺れることで、地震のエネルギーと絶縁されるように設計されているんです。私の入社当時に上司が設計した橋で、いま考えても相当斬新。私自身もかなり影響を受けています。


当時は橋の揺れ幅を1m前後に設定していたんです。けれども震災後の地震力の見直しにより、2m前後揺れても大丈夫なようにする必要性が出てきました。
取り付けた「縦置きサンドイッチ型積層ゴムダンパー」は、地震の揺れによってケーブルが引っ張られると、ゴムダンパーが変形するようにつくられています。そのことによって橋が動くのをやわらかく受け止め、大きな橋桁の移動を制御することができるのです。
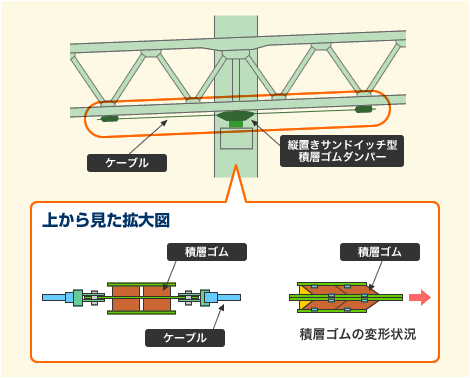
天保山大橋のガセット部に設置したせん断パネルダンパーは、極端な言い方をすれば、スマートに壊れてもらうためのものです。
ある一定以上の力に対して確実に、しかもせん断方向に変形することで、地震エネルギーを吸収し、塔斜材が座屈することを防ぐのです。一部を上手に壊すことで、本体に致命的な損傷を起こさせないという、いわば逆転の発想ですね。
港大橋の制震ブレース同様、世界で初めての試みであり、採用を決定するために、相当苦労しました。


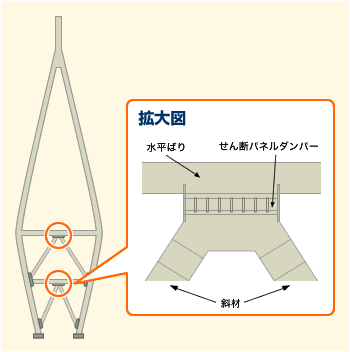

 GISを活用した情報共有プラットフォーム「COSMOS-GIS」
GISを活用した情報共有プラットフォーム「COSMOS-GIS」 高架道路上パーキングエリアの設計・施工
高架道路上パーキングエリアの設計・施工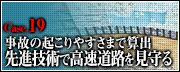 新交通管制システム
新交通管制システム 工事情報等共有システム「Hi-TeLus」
工事情報等共有システム「Hi-TeLus」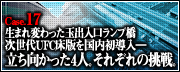 15号堺線玉出入口ランプ橋 リニューアル工事
15号堺線玉出入口ランプ橋 リニューアル工事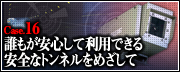 炎強調システム&WDRカメラ
炎強調システム&WDRカメラ 橋梁模型製作コンテスト
橋梁模型製作コンテスト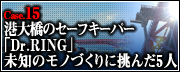 Dr.RINGプロジェクト
Dr.RINGプロジェクト スーパーコンピュータ「京」を使った技術的挑戦
スーパーコンピュータ「京」を使った技術的挑戦 都市部道路トンネルの換気所設計
都市部道路トンネルの換気所設計 阪神高速独自のフレッシュアップ工事
阪神高速独自のフレッシュアップ工事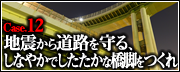 日本初、鋼管集成橋脚の開発と実用化
日本初、鋼管集成橋脚の開発と実用化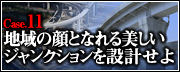 三宝ジャンクションの景観設計
三宝ジャンクションの景観設計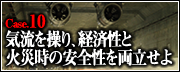 日本初、インバータ制御ジェットファンによるトンネル換気と排煙制御
日本初、インバータ制御ジェットファンによるトンネル換気と排煙制御 阪高 SAFETYナビを活用した交通安全施策
阪高 SAFETYナビを活用した交通安全施策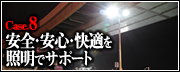 日本初、高速道路本線用LED道路照明
日本初、高速道路本線用LED道路照明 交通管制システム
交通管制システム 保全情報管理システム
保全情報管理システム 地震対策(免震構造・制震構造)
地震対策(免震構造・制震構造) 下弦ケーブルを用いた有ヒンジラーメン橋の補強設計と施工
下弦ケーブルを用いた有ヒンジラーメン橋の補強設計と施工 アルカリ骨材反応対策
アルカリ骨材反応対策 鉄道函体アンダーピニング下に構築する開削トンネルの施工技術
鉄道函体アンダーピニング下に構築する開削トンネルの施工技術 湊川ジャンクション改築工事
湊川ジャンクション改築工事